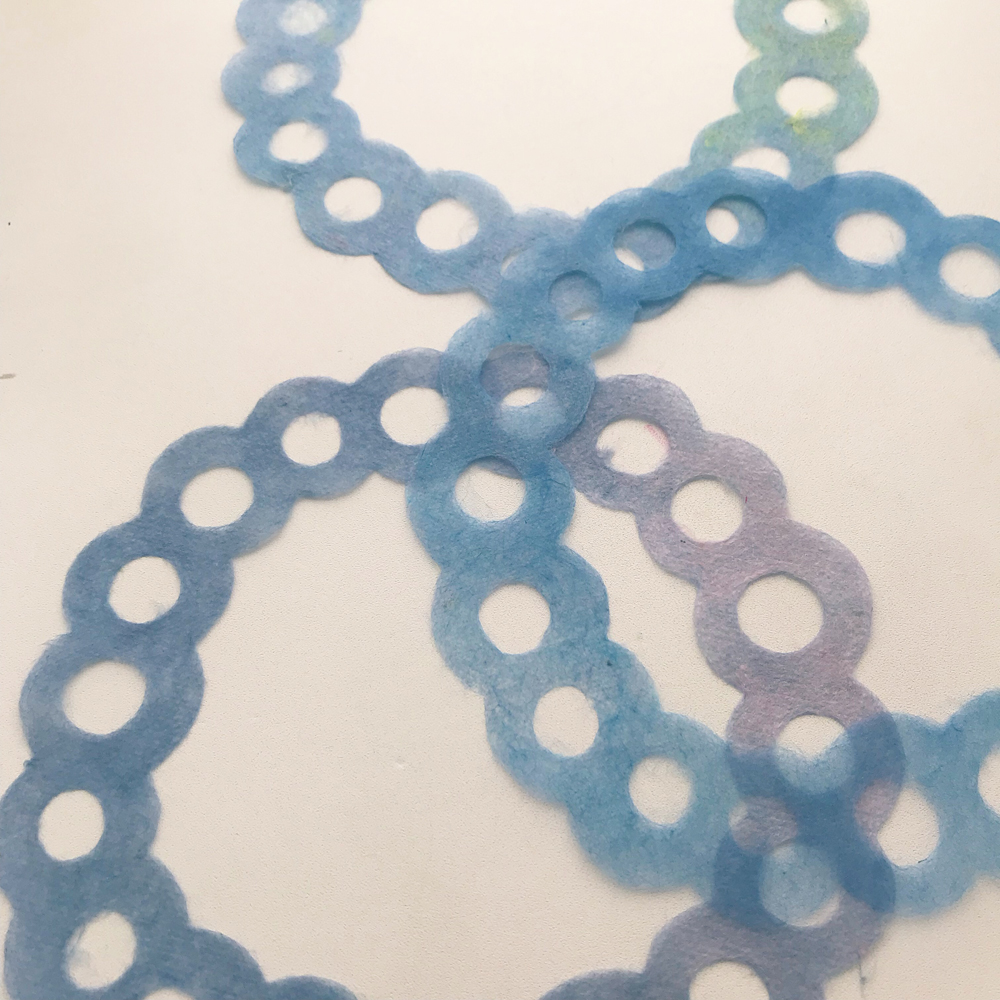窓はたっぷりと結露し、外はまだ暗い。
「だして、だして」と騒ぐ白猫と黒猫を、薄く窓を開けベランダに出してやると、隙間からわたしの呼吸がもれて高く登っていく。
2匹は寒さですぐに「いれて、いれて」と戻ってくる。
2月の朝。
息子はこの2月で10歳になる。
自閉症と知的障害を併せ持ち言葉を持たない息子との10年は、何ものにも変えがたいものだ。
辛いことの方が多かったのは確かだけれど、それすらも今は愛おしい日々だったと思える。
もし神様が現れて「10年前に戻してあげるけど、どうする?」と聞いてきたとしても、私は迷いなく同じ10年を繰り返すだろう。
この10年間でひときわ深い時間といえば、朝の通学の時間。
特別支援学校に入学した彼は、毎朝スクールバスに乗って学校に向かう。
小学1年生から現在まで毎日毎日、雨の日も風の日も、バス停まで二人で歩いた。
たった800メートル、大人の足で10分程度の距離を、30分かけて。

ある晴れた冬の朝、
彼は靴下を履き、リュックを背負い、さあ行こう、という顔で私を見る。
家を出てすぐに60代のご婦人に出会う。
外に出たばかりで、眩しい朝日にも身を切るような冷気にも上手く体と心を馴染ませていない彼は、決して目をあわせず、にこりともしない。
それでも、膝を折って視線の高さを合わせ、根気よく話しかけてくれる。
近所の小学生とすれ違う。
息子の言動をからかう子どももいて苦手だったが、副籍交流(地域の小学校に籍をもち、授業に参加して交流を図ること)を始めてからは顔を覚えてもらえ、爽やかな挨拶をしてくれる。
公園を過ぎ、桜並木の大きな通りに出る。
このあたりから彼に笑顔が現れる。
やっと馴染んできたね、今日の光に。今日という日に。
右折し、またまっすぐ歩く。
息子が大好きな「ゆきおくん・かずちゃん・はなちゃん」の家の前に到着する。
ちょうど私の両親くらいのご夫婦と娘さんのご家族だ。
ある日突然話しかけられてから、毎日のようにご挨拶するのが日課になった。
クリーニング店を営むゆきおくんの家の扉を、息子はそっと開ける。
いつもの笑顔がそこにある。
息子は嬉しくてぴょんぴょん飛び跳ねる。
ゆきおくんたちが笑う。息子も笑う。
私は胸熱くしてその光景を見ている。
ゆきおくんたちと別れたら、私と息子の時間。
冬の通学路はバラエティに飛んで楽しい。
雪が積もっていることもあるし、まだ枯れ葉がどっさり残っているところもあって、わさわさっと蹴散らして歩く。霜柱もザクザク踏んでその感触を楽しむ。
鳥のさえずりにハッとして立ち止まったり、
奇跡的な美しさの枯れ葉を見つけて拾ったり、
ほたり、と綺麗なまま落ちた椿を指の間に挟んで喜んだりする。

白い息を吐き吐き、歌いながら、遊びながら、歩く。
息子が好きそうな曲を適当に選んで歌っていたが、最近は注文がつくようになった。
とん、と鼻をさわれば「真っ赤なお鼻のトナカイさん」
ぴっ、と目をつり目にしたら「こぎつねコンコン」
足をあげたら「トムソーヤのぼうけん」
ねだられれば、何度も歌う。
彼のアクションをとりこぼさないように。
何があっても歌うから、身に付けたその仕草を、どうか忘れないで。
まだ息子が幼い頃、ひとつふたつと出始めていた言葉が、自閉症ゆえまたひとつふたつ、と消えていった。
あの日の恐怖から、私は祈るように歌う。
息子は私の歌を頼りに、空に、アスファルトに、街路樹に、こぎつねの走り回るすがたを見、
トムソーヤーが馬に乗って駆けていく姿を見ている。
これ以上幸せなことはない、という笑顔で。
もちろんいつもこんなに穏やかな朝ではない。
泣きわめく息子を、私も半分泣きながら引きずって歩いたこともある。
おもちゃを持っていくと聞かず、怒鳴り合う朝だってある。
体調が悪くても代わりがいないから、死人みたいな顔でとぼとぼ歩く日も決して少なくない。
いつだって笑顔でのんびり登校というわけにはいかなかった。
朝の眩しい光に向かって溶けるように走り去っていくバスを、いつも鼻の奥に涙の予感を感じながら見送る。
言葉を持たないまま10年生きてきた。
それでも私は、どの母親が我が子を思うのと同じように、彼は光に包まれ希望に満ちていると思う。
祈りに似た行為が、日常の中にありますように。
笑いさざめき
ごはんをつくり
時には喧嘩し
顔を洗い
日々の繰り返しの行為が祈りそのものでありますように。
私の表現するものがその景色に近いものでありますように。
そう願いながら、帰り道はいつも、描きたい物語や和紙造形のことで徐々に頭がいっぱいになっていく。